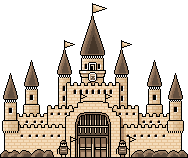<世界文化遺産 3連発>
<上賀茂神社>
上賀茂神社の御祭神「賀茂別雷大神」は、
母である玉依日売が境内を流れる御手洗川に流れてきた
白羽の矢を床に置いたところ懐妊したとされます。
玉依日売とその父の賀茂建角身命は下鴨神社に祀られています。
御祭神である「賀茂別雷大神」の「別雷」とは、若い雷(神鳴り)という意味もあり、
雷を神様と考えていた古来日本人の信仰を伝えています。
<下鴨神社>
御祭神の賀茂建角身命は古代の京都山城を開かれた神さま。
玉依媛命は賀茂建角身命のお子さま。
下鴨神社の歴史は古く平安京が造営される遙か以前から神聖な場所だったのです。
例えば、崇神天皇七年(紀元前90年頃)に、神社の瑞垣の修造がおこなわれた
という記録も残っています。
平安京の造営に当たって、下鴨神社で造営祈願が行われました。
以来、国民の平安をご祈願する神社と定められました。
玉依媛命のお子さん「賀茂別雷大神」は上賀茂神社の御祭神で、
下鴨神社と共に賀茂神社と総称され、
京都三大祭りの一つ葵祭(賀茂祭)が両社で催されます。
<醍醐寺>
醍醐寺は真言宗醍醐派総本山の寺院。
伏見区東方に広がる醍醐山に200万坪以上の広大な境内をもち、
貞観16年(874年)に空海の孫弟子・理源大師聖宝が開山・創建したお寺。
874年の創建当時は多くの修験者の霊場として発展していました。
その後、醍醐天皇が醍醐寺を自らの祈願寺とするとともに手厚い庇護を受けたのです。
その圧倒的な財力によって「下醍醐」が発展していったのです。
「醍醐の花見」は豊臣秀吉や北政所、淀殿らの近親者から諸大名やその配下のものまで
約1300人を召し抱えた盛大な催しで、
秀吉一世一代の催し物と言われています。
※上賀茂神社の特別拝観がお得です!
|

上賀茂神社(楼門) |
立砂は細殿前に作られ、
神様が最初に降臨された
上賀茂神社の北2kmにある神山
を模して作られたそうです。

立砂と細殿(拝殿) |

下鴨神社(楼門) |
太古、この地を占有していた
賀茂氏が創祀したわが国最古の神社の一つ。
祭神として、賀茂建角身命と玉依姫命を祀る。

中門 |

醍醐寺(仁王門) |
空海の孫弟子理源大師聖宝が
醍醐山上に草庵を営んだのに始まる。
五重塔は天暦6年(952年)の建立で、
府内最古の木造建築物
 
五重塔 と 金堂 |

三宝院(唐門) |
1115年に醍醐寺14代座主勝覚が
灌頂院として開く。
のちに仏教の三宝にちなんで「三宝院」となる

「醍醐の花見」に際して、
豊臣秀吉自らが基本設計した日本庭園 |